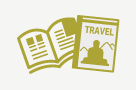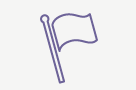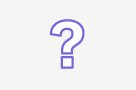鎌倉文士~もうひとつの古都の素顔~

里見邸での新年会。左から真船豊、大佛次郎、里見とん、久保田万太郎、川端康成、中山義秀
鎌倉文士。文壇史に大きな足跡を残した彼らは、鎌倉を語るときに欠かせない存在です。街中を颯爽とゆくその姿は古都の風景の一部でもありました。また、彼らの様々な活動は、町の味わいに独特のスパイスを与えました。文士たちの横顔を拾ってみましょう。
明治22年(1889年)の横須賀線開通は、人と文化の往来を導く契機でした。また、ドイツ人医師ベルツ博士、文部省医務局長など務めた長与専斎博士らの推奨により、鎌倉は保養地としての名声も高めました。これら交通の利便性、住むのに適した温暖な気候が、作家たちを鎌倉へ呼ぶきっかけとなったのでしょう。
「鎌倉文士」という言葉が使われだしたのは昭和に入ってからです。もちろん、それ以前にも"萌芽"は確実に育まれていました。明治から大正にかけての泉鏡花や島崎藤村、夏目漱石、芥川龍之介らの鎌倉滞在は、それぞれに、その執筆活動において重要な意味をもっています。

里見とんと久米正雄。大正13、14年に相次いで鎌倉に暮らし始めたこの二人が、いわゆる鎌倉文士のリーダー格。里見と久米は互いに求心力を発揮し、後に移ってきた文士たちのまとめ役となりました。それを象徴するのが昭和8年に発足した「鎌倉ペンクラブ」です。久米らが中心となって結成されたクラブには、里見はじめ永井龍男、大佛次郎、川端康成、横山隆一、小林秀雄、島木健作ら42人の作家、文化人が名を連ねました。

町の活性化、文化振興面での貢献も忘れられません。昭和9年に始まり、およそ30年間続いた「鎌倉カーニバル」は久米と大佛の発案でした。仮装パレードやダンスなどが町中で繰り広げられるこの祭りは、夏の風物詩として多くの人びとに愛されました。
もうひとつ欠かせないのが「鎌倉文庫」。これは第2次大戦中、切迫する暮らしを打開しようと、文士たちが蔵書を持ち寄って始めた貸本屋です。経営は店番から帳簿管理まで文士が持ち回りで担当しました。読書の機会を失った町の人びとに喜んでもらおう―。「鎌倉文庫」が発足した背景にはそんな願いもあったのです。自ら店番に立った川端康成は後に、当時を振り返り綴っています。「鎌倉文庫は悲惨な敗戦時に唯一つ開かれてゐた美しい心の窓であつたかと思ふ」(「貸本店」より)。
自らが住まいした土地だけあり、文士たちが鎌倉を綴った作品も枚挙にいとまがありません。住んでいた長谷の家に材をとった川端康成「山の音」、肉親の苦悩を七里ガ浜の海とともに描写した里見とん「安城家の兄弟」、鎌倉駅から通勤するサラリーマンの心理を綴った永井龍男「電車を降りて」、燃え上がる炎に滅びの美をみた立原正秋「薪能」等々。本を片手にゆかりの場所を訪ねるのも鎌倉ならではの旅でしょう。もちろん、文学の心は今もこの町に生きています。三木卓、安西篤子、山本道子各氏等多くの作家が暮らしています。鎌倉の魅力はこれからも、数々の小説世界に描かれていくことでしょう。
(写真提供:鎌倉市中央図書館)